読んだ本「物語フィンランドの歴史」「異形の王権」「北朝の天皇」「日本書紀の謎を解く」
何度も言ってますが、年々読書力が低下、理解力も記憶力もどんどん落ちていて、もうあきまへん。
それでも少なくなった脳細胞をかろうじて動かして、ちょっとばかり読んだ本があるので、備忘録として書いておきましょ。
物語フィンランドの歴史〜北欧先進国「バルト海の乙女」の800年
石野裕子著

物語歴史シリーズはどこかの国の歴史をざっくり知るのには、よくできたものです。
新書なので電車の中とか、病院の待合室とかで読むにも軽くていい。
なるべくよく知らない国のものを選んでいます。
で、フィンランドなんてサッカー選手すら思い浮かばず、知ってるのはシベリウス(名前だけ、伝記的なことは知らない)、サンタクロース、ムーミン、マリメッコ、ノキアくらい。
あと、ちょっと前に日本の政治家が「フィンランド化」という言葉を使って、少しばかりの物議を醸した記憶が。
この本で、その発言の「フィンランド化」は妥当な用語ではなかった、ということがわかりました。
しかしとにかく記憶力の低下が激しく、もうすぐ認知症の域に入るのでは?と思うほどなので、この本に登場する人物名もほとんど覚えられず。情けない。
マンネルハイム将軍という軍人で政治家の名前くらいしか覚えられなかった…
固有名詞はともかく、フィンランドが13世紀から600年もの間スウェーデン王国に統治され、その後の100年間も帝政ロシアの支配下に置かれ、1917年12月に独立宣言を行った後は、内乱の時代となり、第2次世界大戦によってようやく一つにまとまった。しかし、ソ連の干渉を受け続け、冷戦時代には外交努力によって独立を保っていた、苦難の歴史を経てきたことは、よくわかりました。
ロシアと北欧の雄スウェーデンとドイツに隣接しているのだから、それは苦労も多かったはず。
自立独立への戦いは歴史上何度もあり、長らく公用語はスウェーデン語でフィンランド語は劣る言語とされていたそうです。
第2次世界大戦では、ロシアとの力関係からナチス・ドイツに与して、戦後は戦争責任を裁かれました。無知なことに、フィンランドがドイツ側についていたとは知らなかった…
スターリンのソ連に侵略されることを恐れ、ナチス・ドイツに与したということですが、どちらについても苦難には変わりなかったでしょう。
おそらく歴史から、自主自立自由を重んじることは強く染み込んでいるだろうと思います。
もう一つ知ったのは、実はこれが1番の衝撃だったのだけど、フィンランド料理は世界一マズイ!
と言われているのですって。
イギリス料理よりまずいらしい…
食べたことないんだけど、どんなものなんでしょ?
異形の王権
網野善彦著
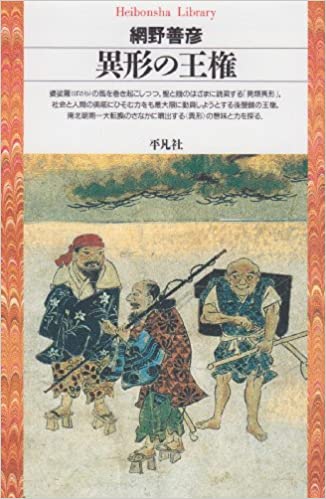
私は以前買って読んだことがあるのに、夫がまた買ってしまった。
もとの本はうちのどこか腐海に沈んでいます。
で、せっかくだから読み直しました。
網野善彦は好きで、かなり読んでいます。
これはいくつかの小編の最後に、「異形の王権」という後醍醐天皇政権についての興味深い論考があります。
初めて読んだ時の驚きは忘れられません。
戦前の聖君、楠木正成のような忠臣の道徳的な物語から、真逆とまでは行かなくても大きく隔たった政権の姿が書かれています。
今回「石つぶて」についての一文も改めて面白く読みました。
読んでいると、中世から南北朝時代の人々…身分の高い人から、庶民までの暮らしぶりや息遣いまでが伝わってきます。
特に、南北朝以降江戸時代から近代至るまで(実態は現在も)、最も差別された人びとについて書かれていることは、今も記憶されるべきだろうと思います。
網野善彦からは、百姓という言葉の意味とか、日本が島国で海外との往来がなかったのではなく、海上交通によって、海外と繋がっていたことなど、教えられることが多くありました。
北朝の天皇〜「室町幕府に翻弄された皇統」の実像
石原比伊呂著

これはとても面白かった。
著者の筆力によるものでしょう、時の天皇や足利将軍、貴族たちの姿が活写されています。
「パパがいうこと聞いてくれないから、ボクやめる」とか、現代語で言うと…みたいなところで、笑っちゃいました。
応仁の乱により、足利将軍家と北朝の天皇家とが同居する羽目になり、毎日両家で飲んだくれていたとか。
南朝、とくに後醍醐政権については戦前の教育もあり、また後醍醐天皇がインパクト強すぎの人だったこともあって書かれたものも多いのですが、この本で北朝について新しく知ることができました。
日本書紀の謎を解く〜述作者は誰か
森博達著
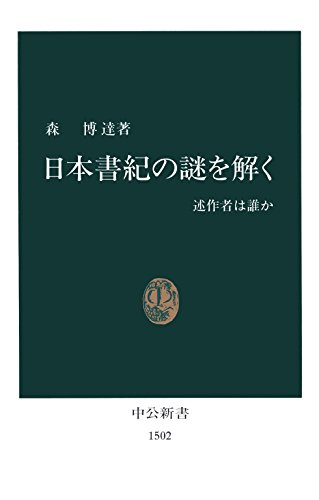
実は私の専攻分野に被るところがある研究を、素人向きにわかりやすく書かれたものです。
中国語、漢文は苦手なので、被るといってもほんのチョビ〜っとですが。
大変興味深く、唸ってしまうところもありました。
ただ素人にもわかりやすく書こうとするあまり、ご自分の経歴などがかなり強く出ていて、また、大変深く研究されたことは理解するものの、ちょっとばかり鼻に着くほど著者の姿が見えてしまうのが残念でした。
それでもその成果はたいそう素晴らしいと思います。
日本書紀の編者は彼によれば…
あ、万一拙文を読んだ人が、これを読みたくなるかもしれないから、結論は書かないでおきます。
しかし、ほんの少しばかりこの手の研究をかじったものとしてはわかるけど、単語の収集とか、同じ音韻の収集とか、手間も時間もかかる大変な作業です。
その単語の山から、何か見えてきた時の喜びは、どんなに大きいかよく理解できます。